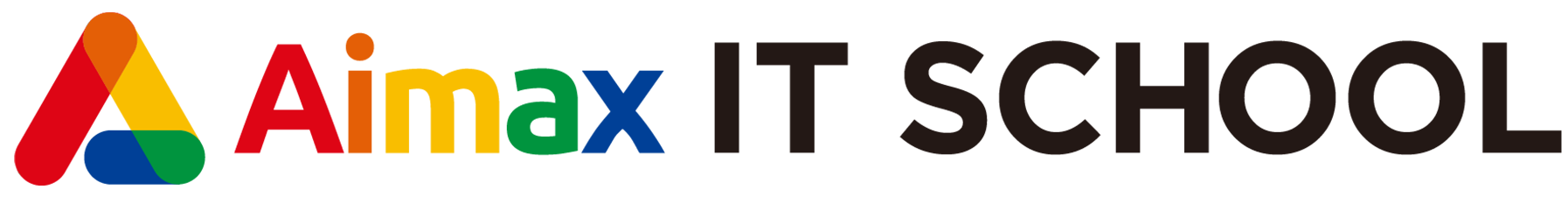【2025年】プログラミングの教え方|コードが書けない未経験の新人・苦手な人を伸ばす教育法と外部研修

プログラミング教育は、企業にとってもはや避けられないテーマになっています。経済産業省の調査によれば、2030年には国内で最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、新人研修の質が企業の競争力を左右します。
(出典:経済産業省「IT分野について」)
しかし実際には「新人がプログラムを書けない」「苦手な人が一定数いる」「説明が難しくて伝わらない」といった悩みを抱える教育担当者も多いでしょう。
本記事では、未経験の新人でも理解できるプログラミングの教え方をわかりやすく解説します。
「新人教育で成果を出したい」「プログラミング教育に失敗したくない」と考える担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ新人教育でプログラミングの教え方が重要なのか
「せっかく採用した新人が、コードが書けなくて現場に入れない…」
「一度つまずいて自信をなくし、早期離職につながってしまった…」
こんな悩みを耳にしたことはありませんか?
実はこれは珍しいことではなく、多くの企業が直面している課題です。
新人が基礎を理解しないまま現場に配属されると、次のような悪循環に陥りやすくなります。
- コードレビューに時間がかかる
- バグや修正工数が増える
- 「自分は向いていない」と本人が感じてしまう
一方で、体系的なプログラミング研修を受けた新人はどうでしょうか。
基礎がしっかり身についているため、OJTだけの社員に比べてバグ発生件数を大幅に減らせるという調査結果もあります。つまり、プログラミングに関わる仕事では、新人教育のタイミングが将来を大きく左右するのです。
もし「自社の教育体制だけでは不安」と感じるなら、まずは無料相談で他社事例や外部研修の活用方法を確認してみてください。小さな一歩が、大きな成果につながります。
プログラミングが全くわからない新人への教え方
プログラミングに初めて触れる新人にとって、コードはまるで「知らない言語」に見えるものです。そのため、教育担当者がいきなり専門用語や複雑な概念を説明してしまうと、学習意欲を失わせてしまいます。
大切なのは「わからない状態が普通」であることを前提に、シンプルなステップで成功体験を積ませることです。ここでは、初心者でも理解しやすい2つの教え方を紹介します。
【教え方1】入力→処理→出力のシンプルな説明から始める
新人には、プログラミングを次の流れで捉えさせるのが効果的です。
- 入力
- 処理
- 出力
たとえば、変数やクラスの仕組みといった「プログラミングの複雑な概念」から教えようとすると、混乱を招きます。対して「入力されたデータを処理し、結果を出す」という一連の流れを実際に体験させた方が、早くプログラミングの全体像をつかめます。
これは、料理に例えるとわかりやすいです。材料(入力)を切ったり焼いたりする(処理)と、料理(出力)ができあがる。この比喩を示すだけでも、初心者は「なるほど、プログラムも同じ仕組みなんだ」と安心して学べます。
最初の一歩でつまずかせないことが、新人教育のカギです。シンプルな枠組みを理解すれば、その後の学習もスムーズに進みます。
【教え方2】失敗体験を恐れない環境を整える
プログラミングを教える際には、「エラーが出るのは失敗ではなく、学びの一部」だと新人に伝えることが重要です。
多くの人は、エラーに直面すると「自分には向いていない」と感じてしまいます。しかし実際には、エラーを修正する過程こそが理解を深める最大のチャンスになります。
事実、エラーを共有・分析できる環境にいる新人は、安心して挑戦できるため、定着率が高まるというデータもあります。
そのため、教育担当者は「エラーを一緒に直す」「質問しやすい雰囲気をつくる」といった工夫で、新人の心理的安全性を守ることが大切です。環境さえ整えば、苦手意識をもっている人でも必ず成長できます。
新人教育は子供向けプログラミング教材から学ぼう
新人教育でつまずきやすい理由のひとつは、「専門用語や抽象的な説明が多すぎること」です。プログラミング初心者にとっては、「変数」「関数」「クラス」といった言葉だけでハードルが高く感じられてしまいます。
その点、子供向けプログラミング教材はとても参考になります。以下に、子ども向け教材のメリットをまとめました。
- 難しい理論ではなく、直感的な操作や具体的な結果から理解できる
- 「できた!」という小さな達成感を積み重ねられる
- 色や動きなど視覚的に理解できる工夫が豊富である
たとえば、Scratchのようなビジュアル型教材は「ブロックを組み合わせれば動く」仕組みなので、初心者に「プログラムは命令を順に実行するだけ」という基本構造を体感させるのに最適です。
そしてこのアプローチは、子供だけでなく社会人の新人教育にも効果があります。なぜなら、抽象的な理屈から入るよりも、動かしてみてから仕組みを学ぶ方が理解がスムーズだからです。
もし社内で導入が難しい場合は、外部の研修会社が提供している「初心者向けプログラミング研修」も検討する価値があります。無料相談やトライアルを活用して、自社の教育体制に合う教材や研修方法を取り入れてみましょう。
\わかりやすい解説で新人教育をサポート/
プログラミング教育の効果を高める工夫
新人研修でプログラミング教育を効果的に進めるには、単に知識を教えるだけでは足りません。理解度の差や苦手意識を考慮しつつ、成功体験や学びを実感できる仕組みを取り入れることが重要です。
ここでは教育効果を高めるための3つの工夫を紹介します。
【工夫1】苦手な人へのフォローアップ方法
どの研修でも一定数「プログラミングが苦手」と感じる新人は出ます。しかし、その状態を放置してしまうと早期離職につながることもあるため、手厚いフォローが欠かせません。
具体的には、次のフォローアップ体制を整えておくのがおすすめです。
- 少人数グループでの補講
理解が追いつかない新人だけを対象に追加の学習時間を設ける - メンター制度
先輩社員が1対1でフォローし、質問しやすい環境を作る - 小さな成功体験の設計
短時間で動くプログラムを完成させ、「自分でもできる」という実感を与える
また、「できない人が目立って孤立する」ことを防ぐ配慮が重要です。心理的安全性を守ることで、苦手な人でも一歩ずつ成長できます。
【工夫2】成功体験を積ませる研修設計
人は「うまくできた」と思える体験を重ねることで、学習意欲が続きます。逆に「難しい・できない」が続くとモチベーションを失いやすくなります。
そのため、プログラミングの教育をする際には、以下の工夫が効果的です。
- 課題をステップ化する
難易度を徐々に上げる - 即時フィードバックする
実行結果がすぐに見える課題を用意する - 成果を可視化する
進捗表やスコアを表示し、成長を実感させる
たとえば、最初は「BMIを計算する簡単なプログラム」をつくり、その後に条件分岐やエラー処理を追加していくなど、成功体験を積み重ねられる流れが有効です。少しずつ「できること」を増やせる研修を設計してみてください。
【工夫3】理解度を可視化するチェックテストの活用
新人教育でよくある問題は、「理解しているかどうかが見えにくい」ことです。特に、講義形式の教え方だけでは、聞いている新人が本当に理解できているのか判断できません。
そこで有効なのが、次のような小テストや確認演習です。
- 毎回の研修後に数問の確認テストを実施する
- 実際にコードを書かせてアウトプットを確認する
- 結果を可視化して「誰がどこでつまずいているか」を明確にする
テストや演習の結果を見れば、早い段階で理解不足を把握し、適切にフォローできます。さらに、本人も「ここが弱い」と自覚できるため、学習の効率が上がります。
【Aimax IT SCHOOL|担当者コメント】
もし「自社で効果的な研修設計まで手が回らない」と感じるなら、外部研修サービスの導入を検討するのも一手です。最新の教材やテストツールを活用した研修で、新人の成長スピードを大きく変えられます。まずは無料相談で事例を確認してみませんか?
教える側が意識すべきポイント
どんなに教材やカリキュラムが整っていても、最終的に新人教育の成否を分けるのは「教える側の姿勢」です。
ここでは、教育担当者が特に意識すべき3つのポイントを紹介します。
逆質問で理解度を確認する
新人に説明していると、「わかったフリ」をされる場面も少なくありません。そこで効果的なのが、次のような逆質問です。
「このfor文は何をしていると思う?」
「いまの説明を一文でまとめるとどうなる?」
このように質問を投げかけることで、新人の理解度をその場で確認できます。逆質問は「理解したつもり」を防ぎ、教育の効率を高める武器になります。
厳密さよりもわかりやすさを優先する
プログラミングの世界には、専門用語や抽象的な概念が多くあります。しかし、新人研修の初期段階では 「正確すぎる説明」よりも「わかりやすい例え」 が効果的です。以下に例をまとめました。
| プログラミング概念 | わかりやすい例え | 補足説明 |
|---|---|---|
| クラスとインスタンス | たい焼き機(クラス)とたい焼き(インスタンス) | クラスは設計図や型、インスタンスはそこから作られる具体的なもの。 |
| 代入演算子(=) | 箱にデータを入れる | 箱(変数)に値を入れるイメージ。「=」はイコールではなく「入れる」の意味。 |
| 変数 | 名前のついた収納箱 | 値を保存して後から取り出せる。ラベルを貼った箱に近い感覚。 |
| 関数 | 調理レシピ | 入力(材料)を渡すと、処理(手順)が行われ、出力(完成品)が返ってくる。 |
| 配列・リスト | 連番のロッカー | 1番、2番…と番号で中身を取り出せるイメージ。 |
| ループ処理 | 工場のベルトコンベア | 同じ作業を繰り返す。条件によって停止やスキップもできる。 |
| 条件分岐(if文) | 信号機 | 状況によって「進む」「止まる」と動作が分かれる。 |
| オブジェクト指向 | レゴブロック | 小さな部品(オブジェクト)を組み合わせて大きな仕組みを作る。 |
| エラー | 赤ペン先生のチェック | 間違いを指摘してくれる機能。修正することで理解が深まる。 |
| コンパイル | 翻訳者が原稿を現地語に変換 | プログラムを機械語に直すイメージ。 |
比喩を使えば、難しい概念もスッと頭に入ります。厳密な定義は後から補足すればよいため、まずは「つかみやすさ」を優先しましょう。
社内での対応が難しいなら外部教材・スクールを活かす
「新人が多くて手が回らない」「教える側も専門知識に自信がない」などの悩みを抱える企業は少なくありません。その場合、外部研修サービスやオンライン教材の活用も選択肢に入れるべきです。
以下にメリットをまとめました。
- 最新の教材や演習問題が整っている
- 専任講師が教えるため、社内負担を軽減できる
- 成果を可視化できる仕組みを提供してくれる
特に近年は、人手不足の影響でなかなか新人教育に手が回りません。十分な教え方ができないと新人も困ってしまうので、もし「社内教育だけでは不安」と感じているなら、まずは外部研修サービスの無料相談を活用して、自社の課題に合う研修スタイルを探すのがおすすめです。
新人教育でよくある課題と解決策
新人教育の現場では、多くの企業が似たような課題を抱えています。
ここでは代表的な課題と、その具体的な解決策を整理しました。
| 課題 | 具体例 | 解決策 |
|---|---|---|
| 学習スピードに差が出る | 早い人はすぐに理解する一方、つまずく人は取り残される | 個別の進捗管理ツールを導入し、弱点に応じた補講を用意する |
| エラーに対する苦手意識 | エラーを出すと「自分は向いていない」と思い込む | エラーは学びの一部だと伝え、講師が一緒に解決する体制を整える |
| 座学中心で実務感がない | 講義形式だけだと退屈になり、理解が浅い | ハンズオン演習や小さなアプリ開発を取り入れる |
| 質問しづらい雰囲気 | 「こんなこと聞いていいのか」と新人が萎縮する | チャットやペアプログラミングで気軽に質問できる環境をつくる |
| 習ったことを忘れる | 数日後にはコードを書けなくなる | 毎日の小テストや、振り返り日報で記憶を定着させる |
| OJT任せで体系的な学びがない | 先輩の教え方にバラつきがある | 研修カリキュラムを標準化し、全員が一定レベルに到達できる仕組みをつくる |
| 離職リスクにつながる | つまずきが積み重なり「自分には向いていない」と退職してしまう | メンター制度を導入し、心理的安全性を確保する |
上記のなかでも実務に直結する課題と、すぐに始められる解決策(対策)について紹介します。
【課題1】未経験の新人でプログラムが書けない
多くの新人が最初につまずくのは「そもそもコードを書けない」という壁です。学校で習ったことがない、文系出身、タイピングやコマンド操作に不慣れ…そんな背景が重なると、最初の一歩が踏み出せず自信をなくしてしまいます。
この状態のまま現場に投入すると、レビューに時間がかかり、周囲の先輩が疲弊する悪循環に陥ります。そのため、次の方法で、新人に成功体験を積ませましょう。
- 「入力→処理→出力」というシンプルな流れを図で見せる
- まずは Hello World など短いコードで「動いた!」を体験させる
- ボタンを押すと画面が変わるような、動きが目に見える教材を取り入れる
「できた」という実感が次の挑戦を促し、最終的には1人でプログラムを書けるようになります。
【課題2】複数名教育するなかで一定数プログラミングできない人がいる
集合研修では、習得スピードに大きな差が出ます。理解が早い人はどんどん先に進みますが、苦手な人は「ついていけない」と感じてモチベーションを失います。
このギャップを放置すると、研修全体の空気が悪くなり、結果的に教育効果が下がってしまうため、次のように、足並みをそろえて教育できる環境を整備しましょう。
- 理解度を可視化できるチェックテストを取り入れる
- 苦手な人向けに補講やeラーニングを用意し、個別にフォローする
- グループワークで「得意な人が講師役」となり、教え合う文化をつくる
こうすることで、「できる人も学び直しになる」「できない人も置いてけぼりにならない」環境が整います。結果として全体の定着率が上がり、教育の効果が最大化されます。
【課題3】教える側としてプログラム説明難しいと感じる
教育担当者の多くが「新人にどう説明すれば伝わるのか?」という壁に直面します。プログラムの世界には専門用語が多く、つい正確に伝えようとしてしまうため、新人は混乱しやすいのです。
たとえば「クラス」「オブジェクト」といった概念をそのまま説明しても、新人にはイメージできません。担当者自身が「説明が難しい」と感じるのは自然なことです。よって、次の教え方を意識して研修を進めましょう。
- 身近な例えを使う
- 専門用語は後から補足し、最初はわかりやすさを優先する
- 社内リソースだけで難しい場合は、外部研修や教材を積極的に取り入れる
「わかりやすく伝える工夫」と「外部リソースの活用」を組み合わせることで、担当者の負担を減らしつつ、教育の質を底上げできます。
プログラミングの教え方についてよくある質問【FAQ】
プログラミングが全くわからない新人に最初に教えることは何?
最初は「入力→処理→出力」の基本サイクルを体験させるのがおすすめです。計算や文字表示など簡単なプログラムで流れを理解し、自分で動かせた達成感を与えることが大切です。
プログラミングが苦手な人を活かす方法は?
苦手でも周辺業務から経験を積ませ、小さな成功体験を重ねることで成長できます。テストやドキュメント作成などの役割を任せながら自信を育てると、数か月後には戦力化も十分可能です。
プログラムを説明するときにわかりやすくするコツは?
専門用語を多用せず、変数を「箱」、クラスを「たい焼き機」と例えるなど具体的な比喩を使いましょう。さらに逆質問を取り入れると、新人の理解度を自然に確認できます。
プログラミングを教えるバイト経験は新人教育に役立つ?
子供向け教室や塾講師の経験は、新人教育にも直結します。相手の理解度に合わせた説明力や質問対応のスキルが身につくため、社内研修でも効果的に活用できます。
まとめ|プログラミング教育は「苦手をなくす」より「小さな成功体験を積ませる」
新人教育で大切なのは、苦手をなくすことではなく小さな成功体験を積ませて自信を育てることです。エラーを一緒に解決できた経験やコードが動いた瞬間の達成感が、成長と定着につながります。
ただし、社内だけで教育を完結させるのは難しい場合もあります。そんなときは、外部研修を活用するのが効果的です。
自社に合った教育方法を知りたい方は、まずは 無料相談で事例やプランを確認してみてください。小さな一歩が大きな成果につながります。
社内教育に悩む企業担当者へ|外部研修サービスの活用で解決
「新人がコードを書けず現場に入れない」
「複数名を同時に教育するのが難しい」
「教える側も説明が難しく、教育に負担を感じている」
こうした課題は、どの企業にも起こり得ます。自社だけで新人教育を完結させようとすると、現場リソースが圧迫され、成果が出にくくなるのが現実です。
そこでおすすめなのが、外部研修サービスの活用です。たとえばAimax IT SCHOOLでは、法人向けに Javaを中心とした実践型プログラミング研修 を提供しています。
まずは無料相談で、自社に合った研修プランや助成金の活用方法を確認してみませんか?